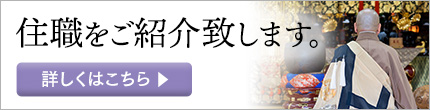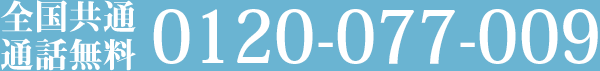ご遺体搬送サービスのご案内
大切なご家族が亡くなられた際、ご遺体を病院から自宅や安置場所へ搬送する必要があります。葬儀社が決まっていない場合や、故郷での葬儀を希望される場合など、まずは一度お電話ください。
ご利用の流れ
- ご依頼
- 24時間365日、年中無休で対応いたします。お電話番号は 0120-077-009 です。
- 準備
- お迎えの場所とお帰り先の住所をお伝えください。お見積り金額も概算でお知らせいたします。
- お迎え
- ご指定の場所にプロのドライバーが寝台車でお伺いします。
- 搬送
- ご遺体は専用ストレッチャーとお布団を用いて、安全かつ丁寧に搬送いたします。
- 安置
- 到着後、ご指定の安置場所へご遺体を移動させていただきます。
- 精算
- 搬送が完了しましたら、移動距離に応じた搬送料金でご精算いただきます。
搬送料金
搬送距離に応じた料金(税別):昼間(8:00~21:00) / 夜間(21:00~8:00)
- 1~20km未満
昼間:14,000円 / 夜間:19,000円 - 20~30km未満
昼間:17,000円 / 夜間:22,000円 - 30~40km未満
昼間:20,000円 / 夜間:25,000円 - 40~50km未満
昼間:23,000円 / 夜間:28,000円 - 50~70km未満
昼間:29,000円 / 夜間:34,000円 - 70~90km未満
昼間:35,000円 / 夜間:39,000円 - 90~110km未満
昼間:38,000円 / 夜間:43,000円 - 110~130km未満
昼間:44,000円 / 夜間:49,000円 - 130~150km未満
昼間:50,000円 / 夜間:55,000円 - 150km以上の場合も距離に応じた料金が適用されますので、詳細はお電話でご確認ください。
注意事項
- お迎え地点
弊社車庫からの距離が基準です。 - 高速道路料金
別途必要です。県外搬送の場合は往復分をいただきます。 - 人件費
400km以上の搬送や、助手が必要な場合は追加料金がかかります(3時間以内20,000円、以降1時間毎に5,000円)。
お問い合わせについて
たまゆら葬社では、お電話に加えてお問合せフォームからのご相談も承っております。ご不明点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。迅速に対応いたします。
- お電話でのお問い合わせ
24時間365日受付中です。
フリーダイヤル:0120-077-009 - お問合せフォームでのご相談
お急ぎでない場合や、詳しいご質問がある際は、フォームからも承ります。