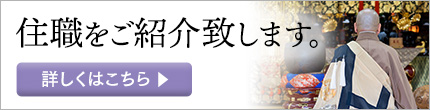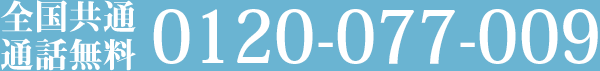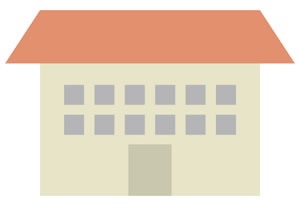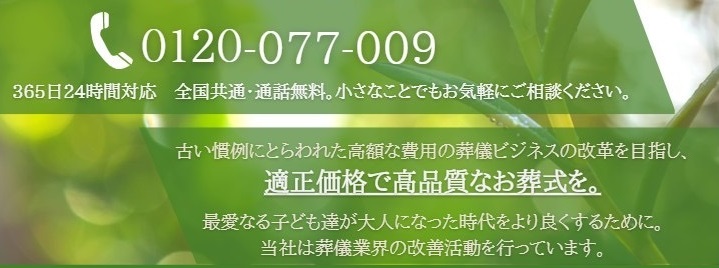せめて最後くらい故人を自宅で寝かせてあげたい・・・
このように思われるのは自然のことです。我々としても故人様と過ごす最後の時間を、家族で気兼ねなく持っていただきたいと考えております。
ご安置ができない状況や事情もさまざまです。更に言えばご自宅へのご安置が絶対に不可能ということもございません。
詳しくお話やご要望をお聞かせいただき、その上でこれからの状況と照らし合わせ、最も最適な提案をさせていただきます。
諸状況から自宅に連れて帰るのが困難な場合
もし下記のような理由から、故人様をご自宅に連れて帰るのを諦めてしまうのは、まだ早いかもしれません。
- 集合住宅に住んでいる住宅事情上の理由から
- 部屋が散らかっていたり、物をどかさなければならない
- 故人の体格が大きいので搬送が難しいかもしれない
集合住宅と一言で言っても、その形状はさまざまです。エレベーターの有無から始まり、更にそのエレベーターの奥の扉が開閉し、ストレッチャーがエレベーター内に収まるのか?大抵の場合、奥の扉には施錠がしてあります。日中、夜間に係わらずその鍵の管理は誰が行っているのか?集合住宅の管理人・管理会社であったり、役員の方達が持ち回りで管理している場合もあります。
それらを事前に把握しておくことで、スムーズに故人様をご自宅へとお寝かせできるでしょう。
そのような状況でなければご安置ができないのか?と、言われればそうではありません。たとえ最上階まで階段で上がろうと、故人様の体格が大きかろうと、ご家族のお力を借りるかもしれませんが、ご要望の限りご搬送いたします。
取り急ぎ、故人様をお寝かせできるスペースさえ確保できれば良いと思います。お掃除もお部屋の配置換えも、私どもでお手伝いできる範囲であればお申し付けください。
近隣の方達に知られたくないという事情

近年の核家族化と葬儀の縮小傾向に相まって、故人様をご自宅に戻さないという選択をされる方も少なくありません。そのほとんどの理由として、近隣の方達に知られたくないという事情があるようです。直葬や家族葬といったご葬儀を要望される方に多いかもしれません。
- 近隣の方達に訃報を知られたくない
- 葬儀の日まで故人を見守れる人がいない
- 葬儀そのものに対する考え方から
故人が一人暮らしであったため、故人宅に連れて帰っても見守れる人がいない。弔問に来られる方への対応や、線香やローソクといった火の番など、葬儀を迎える前に精神的・体力的に疲れてしまう。このような事情も最近ではよく耳にするようになりました。
これらの背景には「知られてしまえば大袈裟になってしまう」、「希薄な近所付き合いなので接し方が分からない」、「仕事が休めず故人を見守れない」といったように、核家族化と忙しい現代人の事情によって、故人様を斎場やお葬式をする式場へ直接ご搬送することになるケースが増えています。
状況や事情を考慮した上で最適なご安置場所の提案をします
まず訃報を受けた際に考えなければいけないことは、故人様を一体どこにご安置をするのか?という点です。現代社会に於ける様々な事項から、
- なぜ故人様を自宅に連れて帰れないのか?
- なぜ故人様を自宅に連れて帰りたくないのか?
後に後悔をしない為にも、これらは認識としてハッキリしておかなければなりません。その後にどのような問題が待ち受けているかなんて、訃報を受けた混乱の最中では考えられる余地がありません。仮にその時誤った判断をしてしまったと思われても、後悔を残さない術はございます。
「故人を自宅に連れて帰りたかったけど、病院から安置所へのご搬送をお願いしてしまった」
このような場合には、葬儀の当日或いはお通夜の日の斎場へのご搬送時、安置所からご自宅を経由して斎場へ向かうことも可能です。更に言えばご自宅に故人様を一度お寝かせすることも可能です。せめて最後に長年住み慣れたご自宅を故人様に見ていただきたいというお気持ちがあれば、このような提案もさせていただきます。
「故人を自宅に連れて帰ったけど、やはり近隣の目が気になる」
スーツや制服姿のスタッフが頻繁にご自宅へ伺うと、どうしても目立ってしまいます。その折には当社スタッフが平服で伺うことをお許しください。寝台車に於いてもいわゆる霊柩車という見た目でなく、一見すると自家用車のタイプにてご搬送に伺います。
故人様のご搬送に関しても、ご自宅に戻られる・ご自宅から出発される時間帯を夜間に対応することも可能です。なるべく近隣関係に目立たず配慮した提案をさせていただきます。