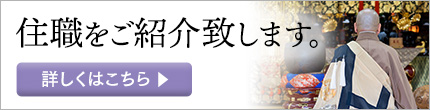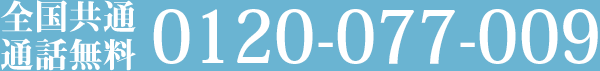故人様への衣服の選び方と納棺の儀式
故人様がお亡くなりになると、病院や施設の職員が清拭(せいしき)を行い、その後、浴衣などを着せてあげます。しかし、着せる衣服に特別な決まりはなく、ご遺族の方の希望に応じて自由に選ぶことができます。
もし故人様に着せたい衣服が決まっている場合は、事前にお伝えいただくことで、スムーズに対応することができます。ドライアイス処置を施した後では体が硬直し、着せ替えが難しくなるため、事前にご希望をお知らせいただくことをおすすめします。最終的には、お棺に納める衣服を選ぶことになることもありますが、柔軟に対応できるようご連絡をお待ちしております。
仏教における納棺の儀式「旅支度」
仏教では、死後は「四十九日の旅」に出るとされています。そのため、納棺の際には、故人様を旅立たせるための「旅支度」を行います。この儀式では、故人様の身体をお身体を覆う形で必要な物を棺に納めます。この作業は、通常、ご遺族の方々で行いますが、希望されない場合は、無理に行わなくても問題ありません。
故人様らしい衣服を選ぶ
「旅支度」を行う際には、故人様が愛用されていた衣服や、ご遺族の方が故人様らしいと思われる衣服を選んで納めることができます。故人様にとって思い出深い衣服を選ぶことで、より温かいお別れができるでしょう。
たまゆら葬社での事前相談・お見積もり
たまゆら葬社では、葬儀に関するご質問や事前相談、見積もりを承っております。お悩みやご不明点があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。ご遺族の方々の負担を少しでも軽減できるよう、スタッフ一同、心を込めてサポートいたします。
お問合せ先
たまゆら葬社:お問合せフォーム
電話番号:0120-077-009
また、インスタグラムで葬儀の施工例を発信しています。是非、チェックしてみてください。
インスタグラムはこちら
どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。