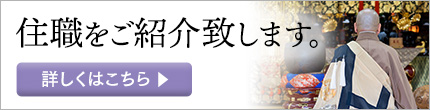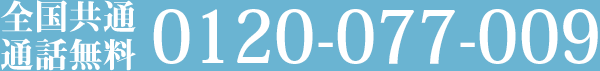現代では、葬儀の形も多様化し、火葬のみを行う「火葬式」を選ぶ方が増えています。少子高齢化や核家族化の進行により、従来の大規模な葬儀から簡素な形式を希望する家庭が多くなってきたためです。
今回は、火葬式の基本的な流れやメリット・デメリットについて詳しく解説します。火葬式を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
火葬式とは
火葬式とは、お通夜や告別式を行わず、火葬のみを執り行うシンプルな葬儀形式です。
「直葬」と呼ばれることもあり、安置場所から直接火葬場に搬送して火葬を行う流れが特徴です。
近年主流の「家族葬」よりもさらに規模が小さく、近親者のみで執り行われるケースがほとんどです。友人や知人を招かない場合が多く、故人とのお別れに時間をかけられない点も火葬式の特徴といえます。
火葬式の流れ
- 安置場所の確保
ご遺体を安置する場所を確保し、火葬式の準備を進めます。 - 日程調整
火葬場の予約状況に応じて、葬儀の日程を決定します。 - 火葬当日
- 納棺の儀を執り行い、故人を棺に納めます。
- 火葬場へ搬送し、火葬を執り行います。
オプションで花祭壇を設け、短時間のお別れを希望する場合も対応可能です。事前に葬儀社へ相談してください。
火葬式のメリット
- 費用の軽減
式場や祭壇の準備が不要なため、葬儀費用が大幅に抑えられます。 - 短時間で済む
通常の葬儀よりも時間が短く、スケジュールの調整が容易です。 - 参列者対応の負担軽減
親族以外を招かないため、ご遺族の精神的負担が少なくなります。
火葬式のデメリット
- お別れの時間が短い
お通夜や告別式がないため、故人とのお別れに時間をかけられません。 - 周囲の理解が得にくい場合がある
簡素な葬儀に対し、親族や知人からの理解が得られないことがあります。 - 後悔のリスク
シンプルな形式ゆえに、後から「もっと丁寧に送り出せばよかった」と感じるケースも少なくありません。
火葬式が選ばれる背景
火葬式が注目される理由は、現代のライフスタイルや価値観の変化です。
核家族化により親族間のつながりが希薄になり、葬儀を小規模に抑えたいと考える人が増えています。また、時間や費用を節約しながらも故人を大切に送り出す選択肢として、多くの方に支持されています。
たまゆら葬社の火葬式プラン
たまゆら葬社では、火葬式プランを 96,800円(税込)~ でご提供しています。
プランに含まれる内容:
- ドライアイス(10㎏)
- 市内搬送(10㎞まで)
- 火葬手続き代行
- お棺
- 骨壺・骨箱
- 仏衣
- スタッフ1名の対応
追加オプションとして、花束や宗教儀式の手配も可能です。ご希望に応じて柔軟に対応いたします。
お問い合わせのご案内
火葬式についてのご相談やお見積りは、以下よりお気軽にお問い合わせください。
また、Instagramでも情報を発信中です。過去の施工事例や最新情報をご覧いただけます。
👉 📷 たまゆら葬社Instagram
たまゆら葬社では、ご遺族の負担を軽減し、安心してご相談いただける体制を整えております。
火葬式をご検討の際は、ぜひ私たちにお任せください。