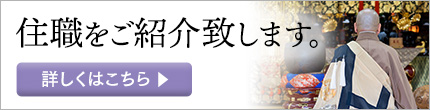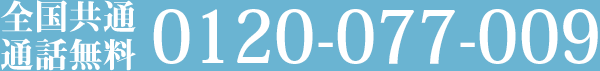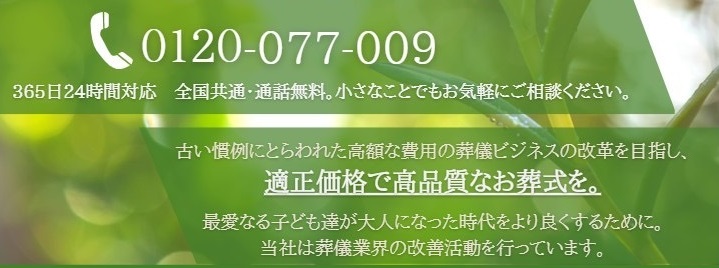位牌には故人の魂が宿る
仏壇は「仏」の「壇」と書きますが、同時にその家の祖先をも祀ります。
と言うより、実際のところは大日如来や阿弥陀如来や釈迦如来などのご本尊よりも、実際に存在を知っているおじいちゃんやおばあちゃんといったご先祖様に対して手を合わせる、という方が圧倒的に多いのではないでしょうか。
火災の際、仏壇は運べなくても「位牌は持って逃げる」という逸話が象徴するように、日本の先祖供養において位牌は非常に重要な存在です。
お盆には仏壇から位牌を取り出し、盆棚に移して祀る地域も多く、仏壇以上に「魂の依代」としての役割を果たしています。
本位牌は、忌明けで祀り、弔い上げで処分する
葬儀後、白木位牌(仮位牌)を使用し、忌明け(四十九日)までに本位牌を準備します。その後、三十三回忌(または五十回忌)で「弔い上げ」とし、以下のような方法で処分されることが一般的です。
仏具店やお寺での焼却供養
墓地への埋葬
寺院による引き取り
これは、死者が個性を失い祖霊となって「〇〇家先祖代々」として集合するという日本的な死者観に基づいています。仏壇が位牌で溢れないよう、弔い上げの後は過去帳や大きなまとめ位牌に移し替え、仏壇を整理します。
位牌の正しい祀り方と位置
仏壇には、以下のような配置が基本とされています。
上段:本尊(如来・観音など)
二段目:位牌(故人の順に並べる)
向かって右側が「上座」とされ、古い先祖の位牌から右に並べます。最近亡くなられた方ほど左寄りになります。
浄土真宗は位牌を作らない宗派
浄土真宗では原則位牌を作りません。
過去帳に先祖の法名などをまとめて記載して仏壇の下段に置いたり、法名を掛軸に表具して仏壇の内側に吊るしてなど、真宗特有の祀り方をします。
浄土真宗の教義では、死後、中陰という期間もなく、遺族による追善供養の必要もありません。
阿弥陀如来に念仏を称えることでどんな人でも救われるという一神教的な教えのため、他宗とは一線を画しています。
ただし、地域によっては真宗門徒でも位牌を作るところもあるようです。
位牌の主な産地と種類
位牌の主要産地は、会津位牌、京位牌、高野位牌、名古屋位牌などがあります。
会津位牌(福島県)
漆塗りが美しく、伝統的な工芸品として知られます。
京位牌(京都府)
千年の都・京都で育まれた精巧な作りが魅力。千倉座・呂門型などの西日本型が多い。
高野位牌(和歌山県)
真言宗の聖地・高野山で発展した宗教用具。丈夫で重厚感がある。
名古屋位牌(愛知県)
金沢に近く、金箔を使った華やかな西日本型が多い。
地域性
関東:唐木位牌(黒檀・紫檀)
関西:塗位牌(勝美・葵角切・京中台)
時代が進むと流通も発達するために、産地的な傾向は昔に比べればなくなりましたが、使われる位牌は未だに地域的な傾向があります。たとえば関東では唐木位牌が多く、塗位牌でも勝美や葵角切などが選ばれています。関西では千倉座や京中台が多いでしょう。
ただし、宗派や男女の決まりなどないので、好みのものを選べばよいでしょう。
家具調位牌・創作位牌の人気
昔ながらの伝統的な位牌ではなく、多様化するお仏壇に合わせたさまざまなデザインの位牌が登場しています。
近年はモダン仏壇に合わせて、以下のような新しいデザインの位牌も人気です。
ウォールナットなど外国材の使用
蒔絵や沈金による装飾
クリスタルやガラス製の位牌
象嵌細工などの伝統工芸を活かした現代風位牌
宗派による制限はなく、好みに合わせて選べます。
位牌のお手入れ方法
唐木位牌
乾拭きが基本
汚れは固く絞った布で拭き取り、必ず乾拭き仕上げ
色入れ彫刻部分はこすらないように注意
塗位牌
金箔部分には触れない
黒塗り部分のみ、柔らかい布で乾拭き
毛払いで埃を取るのがベスト
修理
長年の使用でぐらつく場合、仏具店に相談すると部品の調整や修理が可能です。