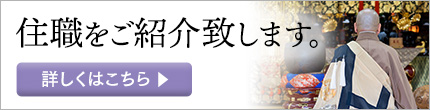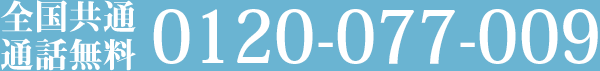1つのお葬式で決めなければならない商品(内訳)は実に多岐に渡ります。
そのため、見積書の明細も大変細かくなっていますが、その内訳の見方を知っておく必要があります。お客様のよくある不満として「見積以上に高い金額を請求された」というものがあります。
「どうして見積もりよりも高い金額を請求されるのか」
〇 葬儀費用の内訳は3つに分類できます
- ①葬儀そのものにかかる費用(祭壇、棺、寝台車、ドライアイスなど)
多くの葬儀社はセットプランを設けています。 - ②飲食や接待の費用(料理や返礼品)
来ていただく方の人数によって数量が変動します。 - ③寺院などへの謝礼費用(お布施・お車代・お膳料・寸志など)
寺院が菩提寺の場合はお布施の金額について葬儀社が介入することはできません。
見積書では葬儀費用のすべてを網羅できるわけではありません。
たとえば、参列の人数が増えれば飲食費も増えるからです。
寺院への謝礼は、葬儀社が紹介する場合は金額に介入することができますが、菩提寺であればそれはできないので、見積書に記載のしようがありません。
良心的な葬儀社では、概算を記載することもあるでしょうが、どこまでを記載するかは葬儀社によって異なります。
また、火葬料や式場使用料は見積もりの内訳に明記されないこともあります。
火葬料や式場使用料など、喪主が直接自治体などに支払う項目については見積書に記載しないケースもあるようです。
ですので、可能な限り、葬儀社は複数を比較検討することをお勧めします。
書面は見やすく構成されているか。
数量変動項目が分かりやすく記載されているか。
喪主が負担しなければならない葬儀費用の総額の目安が記載されているか。
などをチェックして、良心的な葬儀社かどうかを見極めましょう。
ご葬儀のご相談は、公営斎場推奨の たまゆら葬社 0120-077-009 まで ご連絡ください。
インスタグラムにて花祭壇アップしております。